いま知ってほしい!漢方薬の基本のキ

健康意識の高まりや自然派志向の影響からか、ここ数年、漢方薬が注目を集めています。一方で、“漢方薬=自然のものだから体に優しい”といったイメージが先行し、すべての漢方薬が「効き目が穏やか」という偏った思い込みがあるばかりか、健康食品やサプリメントのようなものと考えている人も少なくありません。確かに古くから私たちの生活に馴染んできたものではありますが、漢方薬は“薬”。今では市販薬としてドラッグストアでも気軽に買えるようになり、身近になってきたからこそ、正しく知ってもっと上手に活用したいもの。そこで今回は、長年にわたり、漢方薬に携わってきたロート社員が、疑問や誤解も多い漢方薬についてご説明します。
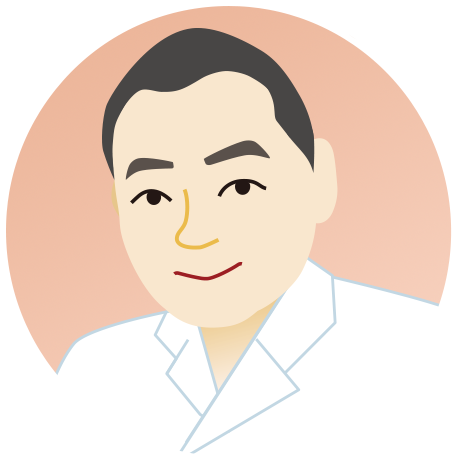
教えてくれたのは、
漢方薬大好き
ロートネーム:ソーマちゃん
実は日本生まれ!?漢方は、日本人の生活に溶け込んできた独自の医学
漢方=中国医学と思われがちですが、実はそうではありません。漢方は日本人に合うよう独自に発展してきた日本の伝統医学です。
また、漢方薬はじっくり穏やかに作用するものと思われがちですが、これも全てに当てはまるわけではありません。時間をかけてじっくり治していくものもあれば、つらい症状にすぐ効くものもあるのです。
Q. 漢方は、中国医学とは違うもの?
漢方とは、「漢(中国)から伝わった方術(医術・医学)」という意味です。といっても、中国医学そのものではありません。古代中国発祥の中国医学が朝鮮半島に伝わって韓国医学が生まれ、中国医学と韓国医学の両方が日本に伝来。それらに日本古来の伝統医学=和方が融合し、発展したものが漢方です。
源流は同じなので、診断や治療、用いる薬物についてなどの共通点はありますが、異なることも多々あります。
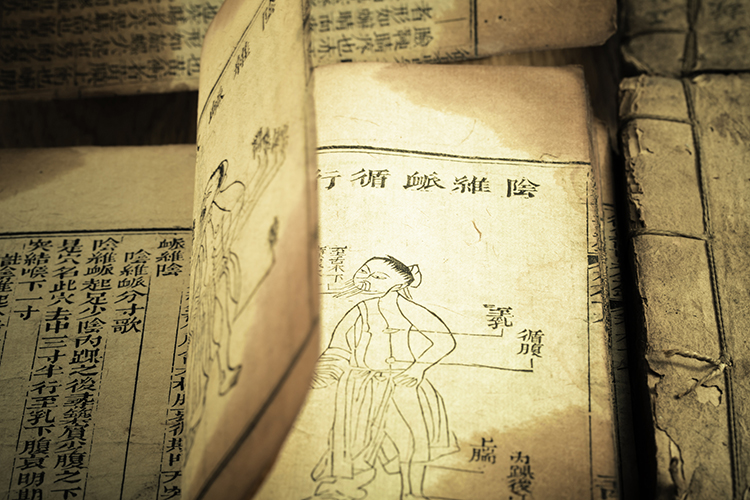
Q. 漢方薬ってどんなもの?何からできているの?
漢方薬は、1種類のものもありますが、通常2種類以上の“生薬”を組み合わせたものです。生薬とは、薬として長年効果が認められてきた天然の植物や動物、鉱物のことで、漢方薬の原料としてよく使われるものだけでも約300種もあり、その多くが植物性です。古代の人々は、経験的に知っていた生薬の働きを症状に合わせて用い、複数の症状に対応させたり、別の生薬を足すことで作用を補ったりしながら、目的に合わせた組み合わせ=処方を誕生させたと考えられています。その後、効果が認められた処方には「名称(方剤名)」を定めることで、より多くの人々を救い、記録・伝承されることになったのです。
Q. 「体に優しい」、「効き目が穏やか」と言われるのはどうして?
生薬でできている漢方薬は“自然の恵み”といえますが、多くの方が持つ「自然生まれだから優しい・穏やか」というイメージは、漢方薬の本質とは異なります。
そもそも薬の目的は、「苦痛から解放されたい」「体を楽にしたい」「悩みを解消したい」からですよね?古くから日常的に使われてきた漢方薬は、そんな目的に応える“薬”なのです。例えば、腹痛や下痢など、すぐに解放されたい症状には、対症療法で速やかに症状を抑えます。一方、冷えや便秘など、急激ではないものの、慢性的に感じる症状や悩みには原因療法を用いて、症状を引き起こしている原因を根本から改善していきます。「効き方が穏やか」というのは、じっくり改善する薬には当てはまるかもしれませんが、漢方薬のほんの一面に過ぎません。

Q. 西洋医学の薬と漢方薬はどこが違うの?
薬の違いの前に、まず西洋医学と漢方医学を含む東洋医学との違いをご説明しましょう。
西洋医学は、臓器や細胞に何かの異常が起きた時に病気になると考えるので、検査で原因を特定し、異常が起きている局所に的を絞って治療します。
それに対して、“心身一如”、つまり体と心を一つのものとして考える東洋医学は、生活習慣や体質、体内の気・血・水のバランス※1の乱れによって病気になると考えます。そのため、検査結果や数値ではなく、本人の自覚症状を重要視して診断し、全体のバランスを整えるよう治療します。このことも、検査では異常が見られないのに不調が続く“不定愁訴”の治療に漢方がよく使われる理由の一つです。
※1 体内の気・血・水のバランス:東洋医学では、気(全身の機能を正常に保つエネルギー)・血(血液とその機能)・水(血液以外の体液とその機能)の三要素がバランス良く体内を循環することで、生命活動を維持すると考えられています。
治療と同じように薬にも違いがあります。例えば高熱が出ている時、西洋医学では熱を下げるために解熱剤の使用を考えますが、漢方医学では、体温の高さではなく、本人が暑がっているか・寒がっているかで診断。寒がっている場合は、熱が上がって発汗する手前の症状(=悪寒)と考えられるので、発汗するまでは体を温めるような処方の薬を使います。このように漢方薬は、その人が持つ自然治癒力を高める治療を行うのです。
西洋医学と東洋医学には、どちらが優れているということではなく、どちらにも得手不得手があるので、そのときの状況、目的に合わせた使い分けが大切です。

コツを知れば難しくない!漢方薬の正しい飲み方
数値には現れない不調を根本から改善してくれたり、本来の自然治癒力を高めたりと、漢方薬は知れば知るほど大人の女性にはありがたいことばかり。でも、「悩んでいる症状に試してみたいけど、使い方が難しそう…」という意見もちらほら。そんな声にお応えして、飲み方についてもご紹介します。
Q. 多くの漢方薬の服用は、“食前か食間”なのはどうして?
薬によって例外はありますが、一般的に漢方薬は、食前や食間の空腹時に飲むことで、吸収がよく、早く効くとされています。食前とは食事の30分~1時間前、食間とは食事をしてから2時間前後が目安です。とはいっても、なかなか時間通りに飲むのは難しいですよね。空腹時に飲むことを考えて、「お腹がすいたら漢方薬」と覚えておいてください。
私がうっかり飲み忘れた時は、薬の種類にもよりますが、食後3時間以内なら飲むようにしていますね。そんな場合でも、次の服用まで2時間は間隔を空けることが大切です。
Q. 煎じ薬でも粉でも錠剤でも効果は同じ?
漢方薬にはもともと煎じ薬のほか、散剤※2や丸剤※3としてつくられたものがあります。現在でも、漢方専門医の処方では生薬を煎じて服用することがありますが、一方で服用が簡便で持ち歩きしやすいエキス錠やエキス顆粒もあり、これらは使い勝手の良さが特長です。効果については煎じ薬のほうが効く印象がありますが、いずれにしても飲み忘れがおきないよう、ご自身の生活習慣に取り入れやすいタイプのものを選ぶことをおすすめします。
※2 散剤:生薬を細かく散にしたもの。「〇〇散」と名付けられている処方が多い。
※3 丸剤:生薬の粉や煎じた薬液を蜜蝋などともに丸い剤形に練り込んで丸くしたもの。「〇〇丸」と名付けられている処方が多い。

Q. 気になる症状がいろいろある時、何種類も飲んでいいの?
症状や悩みがいろいろある時、一見無関係に思えることが、実は同じ原因から起こっていることがあります。その場合、一つの薬で複数の悩みに対応できるのが漢方薬の特徴でもあります。ただし、それを見極めるのは難しいので、医師や薬剤師または登録販売者に相談してください。
Q. 西洋医学の薬と一緒に飲んでもいい?
近年、科学的根拠が次々に証明され、約9割の医師が日常診療で漢方薬を使用しているそうです。実際、医療現場では西洋医学の薬と漢方薬の併用も多く、西洋医学の薬の副作用を抑えるために漢方薬が使われることも少なくありません。ただ、作用が重複するのはよくないので、自己判断で併用することはおすすめできません。医師の治療を受けている方は主治医に、市販薬どうしの場合は薬剤師または登録販売者に相談してください。
生薬の力で体のバランスを整え、本来の自然治癒力を高めるのに最適な漢方薬。根本からじっくり改善したい症状にはもちろん、とにかく早く効かせたいトラブルにも、目的に応じて正しく使えば悩みに応えてくれるはずです。なんとなく不調を感じていたり、日頃から我慢している症状や悩みがあれば、ぜひ一度漢方薬を試してみてくださいね。
・関連記事:ロートの漢方

